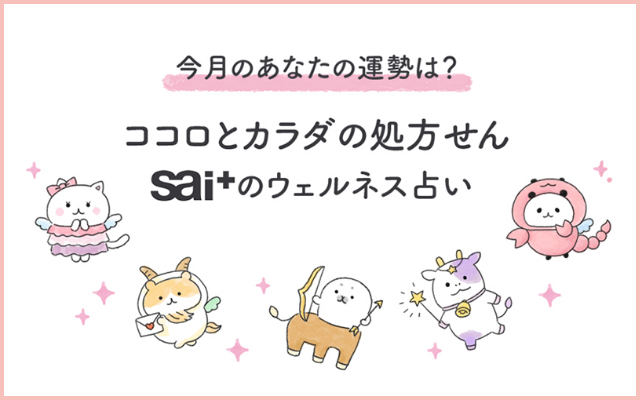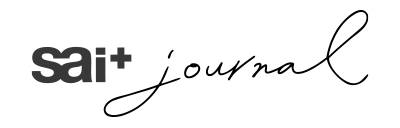生理痛の予防&緩和が見込める食べ物とは? 生理痛を和らげる食事について

毎月1回、辛い症状に悩まされる生理痛。少しでも和らげるために、生理痛の予防や緩和が期待できる食べ物や飲み物について解説します。
生理前後に食生活で気を付けるべきことは?
生理痛に関して食生活で何を気を付けるべきかについて解説します。
そもそも生理痛は、痛みの元となるプロスタグランジンという物質が分泌されることによって起こります。生理痛は、妊娠が成立しなかった子宮内膜をはがすために子宮を収縮させて、経血として体外に排出させるときに起こる痛みなのですが、この子宮を収縮させる役割を担うのがプロスタグランジンという物質です。
プロスタグランジンは子宮を収縮させるだけでなく、炎症を引き起こしたり痛みの原因にもなったりする物質ですので、このプロスタグランジンの分泌量が多ければ多いほど、生理痛の痛みが強くなると考えられています。また、プロスタグランジンは子宮だけでなく血管をも収縮させる作用があり、血管が収縮することによって血液の流れが悪くなります。血液の流れが悪くなると骨盤内でプロスタグランジンが滞ってしまうので痛みが長引いたり強くなったりしてしまうのです。
そのため、食生活で気をつけていただきたいのが、血液の流れを悪くするような食事を摂らないこと、そして、血行を悪くする原因となる冷えを引き起こす食べ物を極力とらないということです。
生理痛の予防が見込める、または痛みや不快感を和らげると言われる食材は?
生理痛の予防や改善の効果が見込める食材とされているのは、冷えを改善し血行を良くする効果が期待される食べ物です。
まず、末梢の血管を拡張させて血行を良くしてくれる食品です。代表的な栄養素がビタミンEです。かぼちゃやパプリカ、アボカド、アーモンドなどのナッツ類、うなぎなどを意識して摂っていきましょう。
また、飲み物ではココアに含まれるポリフェノールにも血行を改善してくれる効果が期待できます。

次に、血液循環を促す効果のある食べ物です。アリシンやジンゲロールなどの成分は積極的に摂っていきたいものです。アリシンが含まれる食品は玉ねぎやにんにく、ネギなど、ジンゲロールはショウガなどに含まれています。特にショウガに含まれるジンゲロールは加熱することでその作用がアップするため、加熱をして食事に取り入れていきましょう。
さらに、マグネシウムを含む食材には、子宮の収縮を緩める効果があるため、生理痛の改善が期待できます。ひじきや納豆にマグネシウムは豊富に含まれています。
生理前・生理中に控えるべき食べ物は?
最後に生理前、生理中に控えていただきたい食べ物についてご紹介します。前述したように、生理前、生理中には血行を悪くしたり、冷えを引き起こす食べ物を控えることがおすすめです。

身体を冷やす食べ物としてまず思い浮かぶのが温度が冷たい食べ物ではないでしょうか。アイスクリームや冷たい果物、冷えた飲み物類は体を冷やしてしまうため極力控えましょう。トマトやキュウリ、茄子といった夏野菜も身体を冷やす作用があるため冷たくした状態での多量摂取は望ましくありません。
血行を悪くする食事として挙げられるのが脂肪の多い食事です。特に、ケーキやチョコレートなど脂肪分の多い食品は、ホルモンの代謝に関わる肝臓の機能を低下させることが知られているため、生理前や生理中の接種は控えましょう。
また、カフェインは血管収縮効果があるため、血行不良となる可能性もあります。例えホットコーヒーであったとしてもコーヒーそのものにカフェインが含まれているため、生理前や生理中の飲み過ぎは控えましょう。

さらに、生理中に鎮痛剤を服用するという方は、アルコールの接種を控えることがおすすめです。アルコールを飲用してさらに鎮痛剤を服用するとアルコールによって作用が強くなりすぎて胃が荒れる原因になりますので注意しましょう。
これらの食材ばかりを食べていれば生理痛が改善する、あるいは和らげる、あるいはここでご紹介した食べ物の摂取を避ければ生理痛が改善できるというわけではありません。
強い生理痛が病気の場合、病気の治療をしなければ改善には至りません。ですので、これらの食材を意識して摂取しても生理痛の強さが変わらない、生理痛や生理時の諸症状が気になるという方は一度病院を受診して検査を受けられることをおすすめします。
参考文献
厚生労働省
エスエス製薬
一般社団法人日本educe食育総合研究所
シオノギ製薬